マインドフルネスの教科書 藤井英雄氏 クローバー出版、合計288ページ、読了時間:約2時間
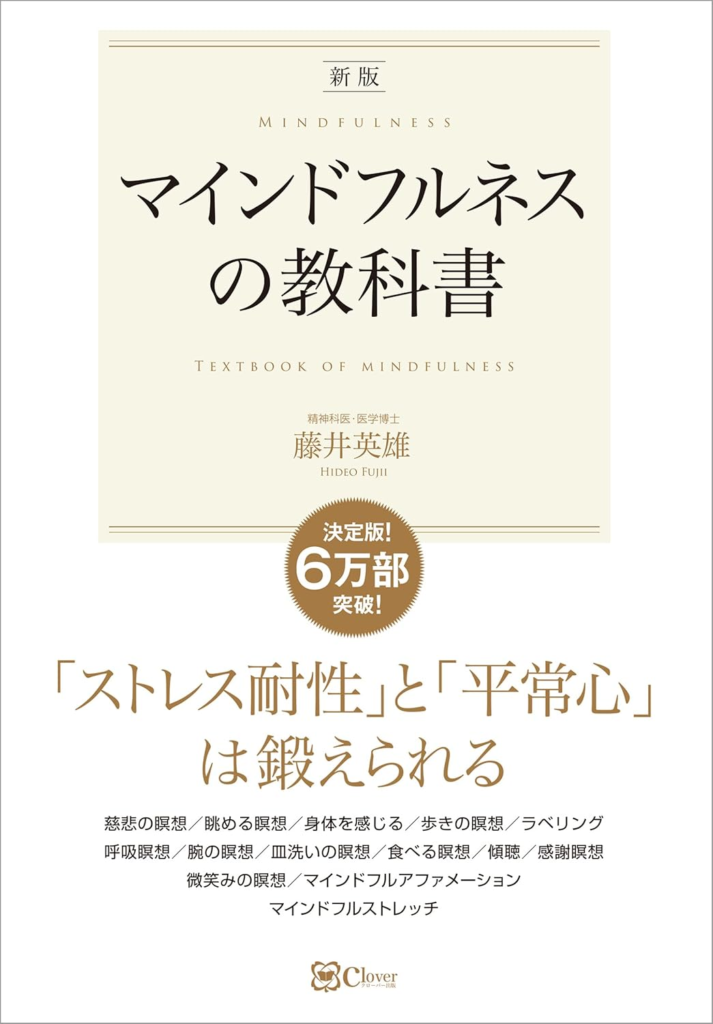
おすすめの読者
- 「彼女がオールする」=「夜遊びしたい、男と浮気するんじゃないか」とネガティブ妄想する人
- 彼女にメンヘラ発言をしてしまい、あとから考えて後悔する行動をとってしまう人
- マインドフルネス=「いまここの気付き」、だから何の役にたつの?という人
- もののけ姫のアシタカのように事実を「曇りなき眼」で見れるようにという人
三行で解説
- マインドフルネスとは、自分をゲーム画面越しで見れるようになること、状態異常(怒り、悲しみ、ネガティブ思考)を画面を通して見ることができる。
- ゲームの中の自分は事実を過去の経験による潜在意識のフィルターを通して認識していることを理解すること。
- ネガティブ思考を無理にポジティブ思考に変えるのではなく、ネガティブ思考越しの思考になっているなと気付くこと、そしてその積み重ねがポジティブ思考に繋がること。
ドッグイヤーの数(自分に刺さったページ):合計39ページ
読んだ感想
小学校時代から国語、現代文の授業は好きだし得意教科だった。公文式にも通っていたが、断然算数、数学より国語が好きだった。理由は、教材を単純に読み物として楽しめるうえに、それを理解していますかという問題に答えプロセスが大好きだった。数学などほかの科目の楽しさは解ける楽しみだけだが、まず読み物としても楽しめる、国語だけは、2度美味しいイメージだった。
それが公文式の教材だったか、小学校の教科書だったか、思い出せないが、31歳の今でもはっきりと覚えている話がある。タイトルも作者も覚えていないが。それは人は「ある出来事」を「事実」そのものとして受け取るのではなく、「色眼鏡」をかけて、その人のフィルターを通して受け取るという内容だった。
小学生当時は、「まあフィルターを通すのは仕方ないじゃん、人によって見方は違うんだし。でもその通りだな。」と納得しただけだった。
ただ31歳の自分は違う、過去の経験からネガティブ思考というフィルターを通して事実をみてしまう。
その場合は大きな問題だ。
今、僕は大好きな彼女がいる。その彼女が「女友達とオールしてくる。」と言ってきた。「事実」はただ「オールして、女友達と飲む」だけだ。女友達は小さい子供がいるので、仕事帰りの旦那に子供をみてもらう夜のほうが都合いいらいしい。
でもぼくには、「オールする」=「実はクラブにいくのでないか、遊ぶ気がないといってもそんな夜中にお酒が入った状態で意志力が弱まり、ナンパされて持ち帰られるんじゃないか、どうせそいつは自分のような根暗で、ひよっこでなくて、タトゥーの入ったウェーイ系なんじゃないか」って、back number の高嶺の花子さんのより想像というより妄想をしてしまう。
半分冗談で、半分本気だ。実際、その日は寝れなくなかった。彼女から夜中の報告ラインをしてもらってもなんとなく不安だった。そしてその後、彼女にオール禁止とメンヘラ前回で、束縛してしまう。病気に近い。当然怒られた。そんな「事実」をフィルターを通した結果、「浮気、持ちかえられる会」になってしまう自分を矯正するための本だった。(AVでNTRものばっか見ていたのも良くないのかもしれない。)
あらすじ解説
マインドフルネスとは今ここにいることと気付くこととはよく聞いている。でもほんで、気づいて何なのかとおもっていた。この本で納得できた。著者いわく、
マインドフルネスとは自分を客観視する技術、私たちは怒りや悲しみ、不安や恐怖などのネガティブ感情にとらわれてしまっている。その瞬間に「自分がネガティブ思考や、ネガティブ感情にとらわれていること」に気づけば(中略)潜在意識の偏った信念から一瞬だけ自由になれる(7~8ページ)
これは自分の解釈としては、ゲーム画面越しに主人公を見ることだと思う。ゲーム画面越しに敵モンスターの攻撃を受けて、混乱しているときは、「もう早く元に戻れ」とボタン連打するだろう。混乱状態で攻撃や防御や行動してもうまくいかない、操作できないからだ。

でも日常生活では状態異常(例えば怒り)の中で、なにか攻撃的な言葉を口にしてしまう。おもってもないことを身近な人に言ってしまい傷つけてしまう。それをあ、ゲーム画面越しにみることで、あ、今怒ってる、状態異常だ、今は何もしないほうがいいぞ、通常状態に戻ってから行動しよう。そう思うことがマインドフルネスと解釈した。
マインドフルネスとは自分がネガティブ思考していることを客観視して気づいていることです。その結果ネガティブ思考によって生まれたネガティブ感情は癒され、思考はポジティブに導かれているのです。
いわゆるアンガーマネジメントとして、怒りが沸いたときに、6秒間我慢するというものがある。これも怒りを抑える意味をあるだろうし、少し距離を置いて客観視しようという意味ではマインドフルネスに近いのかもしれない。
潜在意識と自己肯定感
意識には、フロイトの考え方として、認識できる顕在意識と潜在意識があるという。そしてこの潜在意識というのは、人生の生活のあらゆる経験をもとにゆっくりと形成されていくものらしい。これはもちろん、例えば、「自分は、学生時代毎日ちょっと遅刻していた。遅刻ぐせがある、時間にルーズなタイプだ。その上方向音痴だし、電車の乗換をよくミスしてしまう。だから、とにかく早めに行動するようにしよう、多少遅れてもちょうどよい時間になるように早めに家から出よう」と、良い習慣づけになる場合もある。
しかし、過去の失敗体験や怒られた経験から潜在意識としてネガティブ思考が形成されてしまう。さらには、著者は”偽りのヨロイ”という幼少時代の概念もあげている。
小さい子供のころ、私たちは一人では生きていけなかった。身近にいた大人たち、とくに親がいなければ生活と安全を守れませんでした。だから大人たちが望む価値観を受け入れ、自分の欲求を我慢して生きてきたのです。79ページ
それどころか大人になると、このヨロイを使えば使うほど、自己肯定感を弱くするという諸刃の剣です。自分の欲求を我慢し、他者の欲求に従ううちにやがて自分を否定してしまうようになる。
まあ、反抗期もあるよね。。。と思ってしまうが、自分自身もわりと親の言う事を聞いて生きてきた人間だ。とくに母親は何かしようとするととにかく、「無理やからやめとき」とか、「危ないからやめとき」とか口うるさく言われたものだ。とくに覚えているのは、大学生時代に海釣りに行くと言ったら、「同じ小学校のXXXさんのところの兄弟は海釣り行ったときに溺れて亡くなったやて」とか言われた記憶がある。「なんで行く前にそんなこと言うのか」と怒った思い出がある。ネットの世界でいわゆる毒親がなんでも禁止にしたせいで自分はなにもできない無気力な人間になった。だから引きこもりニートになったなんていうのも聞いたことがある。さすがにそれは自分の甘えだろとも思うが、自分もネガティブ思考の人間だから同じ種類なんだと気づいた。この母親のコメントはコメントで母親の愛であると思うし、このあたりは「愛するということ フロム」を紹介するときに記載したいと思う。
冒頭の色眼鏡、フィルターの話にもどるが、要は潜在意識として幼少時代から培われた経験や、偽りのヨロイ、また人間は成功より失敗に注目しがちなどの特性から、事実をネガティブフィルターを通して捉えてしまう。彼女が女友達とオールするだけ⇒自分のネガティブフィルター⇒彼女は浮気する、持ち帰られるという思考だ。
これをマインドフルネスによって、あれ、今はただの事実はオールするなのに、えらい飛躍した妄想をしているぞと気づくこと、またそのことで、ムカついたり、イライラしている自分に気付くことそれがマインドフルネスのようだ。
外界の現実⇒身体⇒潜在意識⇒思考⇒感情⇒意思⇒潜在意識⇒身体⇒言動⇒新しい事実
この中のどれでも良いのです。ハッと我に返った瞬間、マインドフルネスが起動した瞬間がチャンスです。このチャンスを有効活用し、マインドフルネスにネガティブ思考を手放すことができたら潜在意識の自己肯定感が強化されるのです。
自分はタバコを吸わない、職場でも、飲みの場でも、最近は禁煙のところも増えているので、タバコの匂いをかぐ瞬間もほとんどない。それに加えて、直近で父親が長年の喫煙で大きな病気になってしまった。(今はいったん経過観察中であるが)それ以降、歩いていて、路上喫煙している人をみると、呼吸を止める、めちゃくちゃムカつく。もはや嫌煙家になってしまった。
私たちは子供のころから、人の迷惑にならないようにしなさいと教えられてきました。そして迷惑をかけたときは𠮟られてきました。いつしかその教えは私たちの潜在意識となり、「迷惑をかけていはいけないという信念を形成し、迷惑な行動を躊躇するようという行動ができました。
これは迷惑をかけたら批判されるからです。これも「偽りのヨロイ」のパターンです。
怒りを感じているとき、潜在意識意識としてこの信念「迷惑をかけてはいけない」が動いているケースがたくさんあるのです。
自分に禁じているから、他人にも禁じたくなるのです。
その結果、自分の行動が他人に行動に支配されているのです。
自分に許していないから他人を許せなくなるのです。
まさにそうだ。別に他人が路上でタバコを吸ってようがどうでもいいのだ、でも気になるのは自分に禁じているからだと思った。別に父親が倒れる前からもともとタバコを吸っているわけではないが、自分はタバコなんかダサいものだ、それを律しているのだという潜在意識からタバコを毛嫌いしているのだと気づいた。タトゥーを見下すのもそういうことだろう。自分はしていないのにという考え方だ。
別にすべての犯罪を許せというわけではないと著者は言っている。でもタバコで路上喫煙している人をみてイライラするくらいなら、ほっておく方が自分の人生に得だろうという発想だ。これもマインドフルネスで、あ潜在意識としてこう考えているからイライラするんだなと思えば、すぐにではないが、イライラしなくなるだろう。
聖書の「もしだれかがあなたの右の頬を打つなら、左も向けなさい」(マタイによる福音書)もそういうことかもしれない、ちょっと違うだろうけど。
マインドフルネスの鍛え方
いわゆる瞑想などのマインドフルネスに意識してなる方法(感謝の瞑想、呼吸瞑想、皿洗いの瞑想、歩行瞑想など)と、”A:意図的にマインドフルネスになる方法”と
日常生活で怒りや悲しみなどの感情に支配されているときにハッっと我にかえる、気づくという”B:偶然のマインドフルネス体験を有効活用する方法”の2つがある
Aの方がまさにマインドフルネスのイメージどおり、なにも考えずに呼吸に集中して瞑想しようという一般的なイメージのマインドフルネスで、こちらはスポーツでいう素振り、フォームを覚える方向の練習である。こちらについては世間一般に知られているマインドフルネスのやり方が記載されていた。
もう一方のBの方は、まさに実践練習、本番環境での練習ということになる。こちらもラベリングと言って、自分の感情に名前をつけて俯瞰的に実況中継することが記載されていた。こちらもネットですぐ出てくるので割愛。
まとめた感想
マインドフルネスの実施方法、瞑想の方法などは、もはや世間一般に知られているもので、別にネットで検索したり、YouTubeでみれば十分に情報を入手できるだろうと思う。
この本の良いところは、そのマインドフルネスの効果として、ネガティブ思考に陥っている自分を客観視する癖がつき、あ~また変な妄想していると気づくことでネガティブ思考の連鎖から抜け出すこと、そしてその気づきを繰り返すことで、自己肯定感を高くなり、ポジティブ思考な生活を送ることができうるようになるよということだと思う。
よくするためにやろうというところ、そしてなぜ自己肯定感が良くなるのかについて記載されているところが良かったと思う
彼女の行動をできる限り事実として捉えるように、もののけ姫のアシタカのいう「曇りなき眼で見る」ために、マインドフルネスな生活を送ろうと思う。
この本の出版は初版が2016年8月、新版が2019年、自身の購入日が2021年で、まともに読まずに実家に眠らせていた。今まさに自分のネガティブ思考で彼女に迷惑をかけているので、なんとなく読んでみたが、まさに良いタイミングだったと思う。
はじめての本紹介としては、ちょっと宗教くさいというか、クローバー出版のホームページもちょっとうさんくさい感じで、ちょっと嫌な部分ではあるが内容はすごく良かったし、タイムリーだったのでこの本をはじめての本紹介とした。
2025年2月26日:初投稿
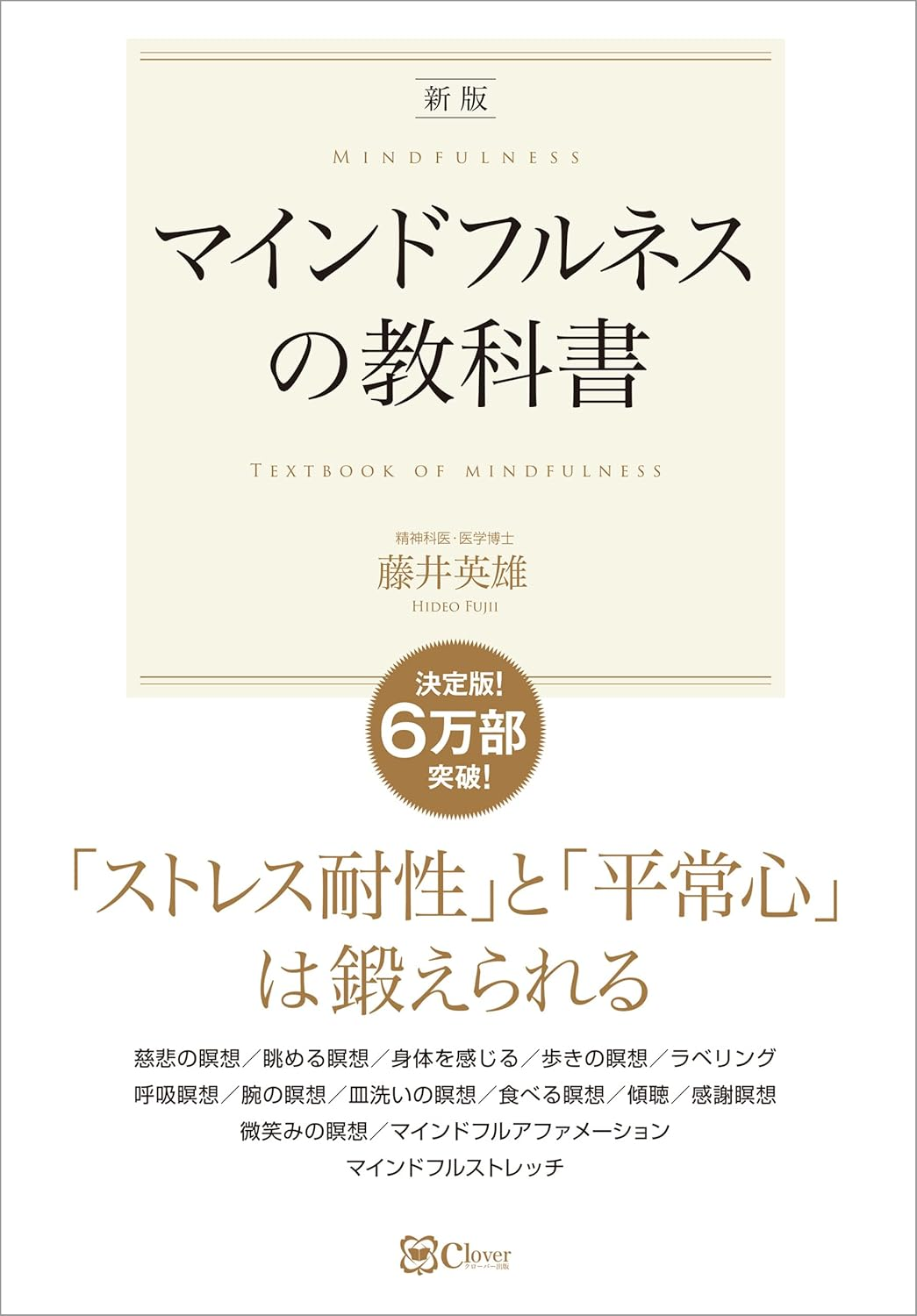


コメント